
相続の基本
相続できる親族の範囲は民法で決められていて、これに該当する人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人の中でも、民法で相続の優先順位が定められており、その相続順位に従って遺産相続が決定します。
また、被相続人は亡くなる前に遺言を残すことができます。遺言とは、故人が生前残した意思表示をその人の死後に効力を持たせるための手段です。遺言により自分の財産を自由に処分できますが、遺言が法律上の効力を生じせしめるためには、民法の規定に従って作成されていなければなりません。

相続のスケジュール
身近な人が亡くなり、相続をすることになった場合、何から始めていいのか分からないという悩みを持っている方も少なくないでしょう。
相続の手続きは、複雑なものや、期日が定められているものなど、さまざまな"穴"があるものばかりです。また、相続分や遺産分割などに関しては、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性も考えられます。
そのため、相続ではそれぞれの手続きの期限を意識したスケジュール管理が必要となります。

相続税の節税対策
相続税は、相続によって取得した財産について課税される税金です。少し厳密にいうなら、相続財産の金額から控除という非課税枠の金額を差し引いた部分に課される税金といえます。この金額に、所得財産額に応じた相続税率を掛けたものが、相続税の額になります。
このことから、相続税を抑えるためには、①相続財産の金額を抑える、②控除額の金額を増やすという2種類の方法があります。①の例としては、生前贈与や建物の賃貸、更地への建築という方法があります。また、②の例としては、配偶者控除の利用や生命保険の活用などがあります。幅広い節税テクニックを抑えれば、効果的な対策ができることでしょう。
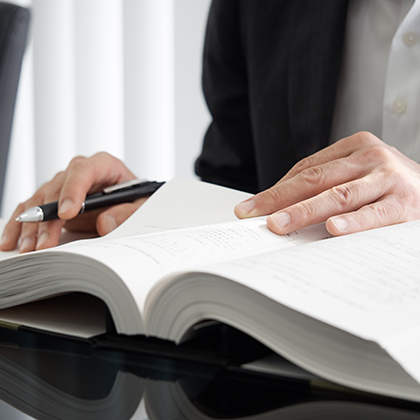
相続税の税務調査
税務調査と言えば、会社や個人事業の決算書をチェックするために税務署の職員が訪問することを想像しがちですが、相続税にも税務調査はあります。
相続税の税務調査は、一般的に主に資産総額が高額な方や、海外にも資産がある方を対象に行われますが、資産総額がそれほど大きくなくても税務調査が入るケースはあります。そのため、相続の際にはたとえ資産総額がそれほど高額でなくとも、控除額を超えていれば、法律上の手続きに沿って相続税の申告を行う必要があります。
相続税には多くの制度があり、申告から納税まで複雑なものとなっています。相続税でお困りの際は、税理士に相談することをおすすめします。

相続のスケジュールと遺産分割
相続は、家庭内の紛争に繋がりやすいシビアな問題です。
仲の良かったご家族でも、お金をめぐる相続トラブルを機に疎遠になってしまうことがよくあります。疎遠になるだけならまだしも、家族同士で裁判になってしまうことさえもあります。
トラブルに発展しやすい相続・遺産分割は専門家にご相談いただくことがおすすめです。トラブルを未然に防ぐとともに、期限が設けられている相続税の申告や準確定申告などの手続きもスムーズに進めさせていただきます。

相続の手続き
相続にはさまざまな手続きがあります。生前までさかのぼれば「遺言」の作成や「生前贈与」などがあり、死後には「遺産分割協議」や「相続税の申告・納税」、「相続登記」などの手続きがあります。
これらの手続きは非常に煩雑で、特に複数の財産(「不動産」と「預貯金」など)を相続する場合には、それぞれの財産で相続方法が異なるため、ますます手続きが複雑になります。
複雑な相続の手続きは、トラブル防止も兼ねて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談すれば、細かな制度面もクリアしたうえで、ご家族に一番合った相続手続きを実現することができます。









